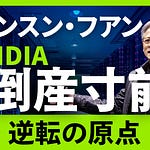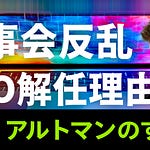サム・アルトマンがポール・グレアムからYコンビネータ(YC)の社長職を引き継ぎ、同時期にイーロン・マスクとAI研究所設立に向けた議論を重ねていた時代。
本エピソードでは、OpenAI設立へとつながる「前夜」の動きを追いかけます。
Yコンビネータのスケール戦略、サムの「資金調達の天才」としての才能がどう開花していったのか。
そして、イーロン・マスクが感じていたAIへの危機感と、Google DeepMindへの対抗心。
それらがどのように交差して「非営利のAI研究所 OpenAI」という構想につながっていったのかを、具体的なエピソードとともに解説します。
目次
00:00 前回までのあらすじ
03:47 イーロン・マスクとの出会い
08:08 AI研究所初期の構想
10:38 非営利組織として生まれた別の理由
12:27 次回予告
エピソードの概要
今回のエピソードでは、次の3つの流れを中心にストーリーが展開します。
Yコンビネータ社長としてのサム・アルトマン
ポール・グレアムからのバトンタッチ
YCの投資先が8社から80社規模へ拡大していく過程
年金基金や大学財団など、機関投資家を巻き込んだスケール戦略
サム自身が「ビジョナリー」「伝道者」「ディールメーカーの神」と呼ばれるようになっていく背景
イーロン・マスクのAIへの危機感と、出会いの文脈
2015年前後、世界初のAI安全性会議(FLI主催)やAI倫理委員会の動き
マスクがAIを「人類滅亡のリスク」と本気で捉えていたこと
Google DeepMindとその倫理委員会に対する強い不信感
そうした文脈の中で、サム・アルトマンとマスクが毎週のように食事を共にし、AIについて議論を深めていったプロセス
OpenAI設立構想と、「なぜ非営利だったのか」
サムが提案した「AI版マンハッタン計画」というイメージ
Yコンビネータ Research内のプロジェクトとして構想された最初期のOpenAI
研究者への報酬をYC株式で支給するモデル
「高度に安全であればすべて公開する」「非営利であること」が掲げられた理由
研究者への訴求ポイントとしての非営利
サム自身がYC社長の立場のまま、別組織のトップになれない事情への対応策としての非営利構造
マスクが資金提供を約束し、名称を「OpenAI研究所」とすることを決めた経緯
当時の学術界からは「失敗する」と見られていたにもかかわらず、それでもプロジェクトが動き出した背景
この一連の流れが、後にサムがYコンビネータ社長を退き、OpenAIのCEOへ専念していく流れにつながっていきます。
さらに、最初期に「非営利組織」として設立されたことが、後年のOpenAI内部の亀裂やガバナンス問題にも影響していく伏線であることも示唆されます。
Takeaways
・サム・アルトマンは「プロダクトの人」以上に、「資金調達・スケールの設計」に真価を発揮していた
・Yコンビネータで培われた、機関投資家を巻き込む発想やディールメイキングのスキルが、そのままOpenAIの資金調達戦略のベースになっている
・イーロン・マスクは、AIの安全性を本気で懸念していたからこそ、Google DeepMindに任せきりにすることへの危機感を強めていた
・サムとマスクの「毎週のディナー」と継続的な議論が、AI研究所構想を現実味のあるプロジェクトへと変えていった
・OpenAIが非営利としてスタートしたのは、研究者への訴求だけでなく、サム自身のポジションや政治的な事情も含めた、極めて戦略的な選択だった
・設立当初は学術界からも懐疑的に見られていたが、サムの「資金調達の神」としての評価と、マスクのプレゼンスによってプロジェクトは前進した
・この「非営利スタート」という設計が、後のOpenAI内部の分裂やガバナンス問題を語る上での重要な伏線になっている
参考文献
このシリーズは、以下の書籍の内容をもとに構成・考察を行っています。
『サム・アルトマン:「生成AI」で世界を手にした起業家の野望』
ニューズピックス
キーチ・ヘイギー (著), 櫻井祐子 (翻訳)
次回予告:OpenAI創業メンバーとスタートアップとしての空気感
次回のエピソードでは、いよいよOpenAI設立後の話に入っていきます。
・創業直後のOpenAIはどんな雰囲気だったのか
・サム・アルトマンの「右腕」となったキーパーソンは誰なのか
・なぜ、当初は学術界から冷ややかに見られていたにもかかわらず、優秀な研究者たちがOpenAIに集まってきたのか
・そこからChatGPT登場へと至るまでの布石
こうしたテーマを掘り下げていきます。
ぜひ次回もお楽しみに。では、また👋
Lawrence